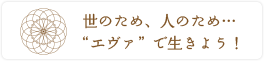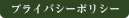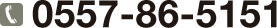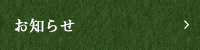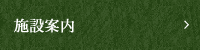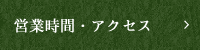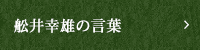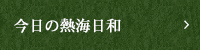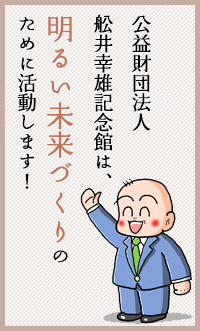熱海日和
第28回新春講演会 講演録 後編
(今回は前編に続いて後編をお届けします)
第3部は舩井幸雄記念館、館長の佐野浩一です。
三代さんとジョシュさんからのお話を受けまして、館長の佐野からは、「違い」についてのお話しや今回の講演会のタイトルである「幸感力」(幸せを感じる力)について紹介しました。
【違いを大切にしよう!】
一人一人の顔や体の大きさが違うように一人として同じ人はいません。
ということは、モノの考え方や捉え方なども違いますよね…
とくに同じ民族だけで暮らしている日本はその典型で、みんな同じであることが求められ、違うものは避けられてしまう傾向があります。
最近ではバリアフリーという言葉やLGBTQという言葉が浸透してきて少しずつ変わってきているようには思いますが、言葉だけが独り歩きしているようにも思います
まずは「違い」を知ること、そして、受け止めて受け入れることが大切だとお伝えしました。
【幸感力って!】
「幸感力」
なんとなくイメージが湧くと思うのですが、はじめて聞いたという人が多いと思います。
実はこの言葉、館長の佐野浩一が作った言葉なのです…
意味は漢字を読んだままで、幸せを感じる力のことです。
館長の佐野浩一ですが、実は昨年の12月末に脳梗塞になりました。
早期発見、早期に治療ができたので、幸いにも大きな障がいなどは出なかったのですが、最初の3日くらいは治療のためベットから動いてはいけなかったとか…
この世に生まれてから60年、健康で大きな病気もしてこなかった父にはかなり堪えたようです!
入院中は時間があったので、いろいろ考えたそうなのですが、
「幸せ」っていうと、言葉が大きすぎるのでイメージが掴みにくいが、健康であることや、自分で動きたいように動けるこはって本当に幸せなことで、実は近くに「幸せ」ってたくさん転がっているのだなぁと気づけたことが、病気を通しての大きな学びになったと話していたのが印象的でした!
「自分は幸せだ!」と、たくさんの人が言える。
そんな世の中を目指していきたいですね!
そして、イベントの最後にはゲストのお2人と館長の佐野と、佐野純平で座談会を行いました。
三代さんからは、ご自身が実行委員長を務められている「ゆいまーるビーチフェス」の話しや、そこで出会ったある少女との話し、ジョシュさんからはユニバーサルツーリズムについてや熱海のバリアフリーのこれからについてお話しいただきました。
私からは、館長のお話しにもありましたが、「違い」についてお話しさせていただきました。
わたしも自分が当事者になるまでは知りませんでしたが、車いすを使って生活している人もみな「違う」ということです。
偶然にも三代さんとジョシュさん、そして私。
みな違った要因から車いすを使って生活しています。
三代さんはバイク事故で首の骨を折り、頸髄損傷。首から下の運動機能に障がいがあるために車いすを使っています。
手で車いすを動かせるので手漕ぎの車いすを使われています。
ジョシュさんは脳性まひという先天性の病気のため車いすを使われていて、手足を動かすのが困難なため、電動の車いすを使われています。
そして私は23歳の時に脳梗塞になり、身体の左側に麻痺があります。
歩くのが難しく、車いすを手で動かせないので、電動の車いすを利用しています。
それぞれの背景により、できることやできないことも違ってきます。
紹介していくとキリがないので、このあたりにさせていただきますが、車椅子ユーザーでも、みんな「違う」「個性がある」ということがわかっていただけたのではないかなと思います。
お伝えしたいことがありすぎて大変長くなってしまいましたが、
最後に、最初のテーマに戻らせていただきますが、「バリアフリーとは人の心だ!」ということです。
これは、エレベーターやスロープ等、もちろん優れた設備は必要です。
しかし、それを最大限に活かせるか否かは「人の心」です!
三代さんは車いすで世界一周をされているときにそれを痛感されました。
世界のあちこちでたくさんの人に出会い、彼ら、彼女たちに助けてもらえたから世界一周ができた…
ジョシュさんは、単身で日本に来られ、日本で生活されています。
その中で,たくさんの愛や優しさに触れられてきました…
早いもので私も車いす生活になって6年です。
車いすユーザーになったことで、人は1人では生きられないということや、たくさんの人に支えられて生きているという事を身をもって感じる日々です…
これから、三代さんやジョシュのように「バリアフリーとは人の心だ」ということを,わたしも伝えていけるようになりたいと思います。
講演会の開催にあたって、ジョシュさんがお仕事をされているアゼリーグループの理事長で医学博士の来栖理事長。
熱海市内を中心に介護タクシー事業を営まれている「伊豆おはな」の河瀬ご夫婦に大変お世話になりました。
ありがとうございました。
そして、ご来場いただきましたお客様、オンラインでご視聴くださいましたお客様、どうもありがとうございました。